労務事情2017年11月号掲載
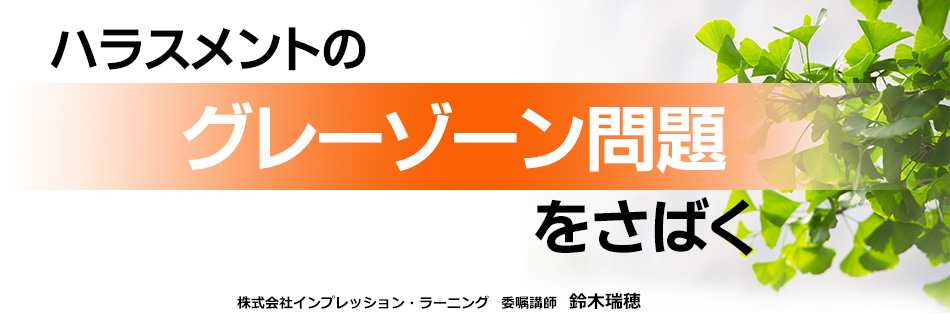
[第1回] ハラスメント問題の押さえどころ
ハラスメント問題の押さえどころ=
グレーゾーン問題
これから8回シリーズで、ハラスメントについてのお話をしたいと思います(なお、このシリーズでは、ハラスメントという言葉をセクシュアルハラスメント〈以下、セクハラ〉とパワーハラスメント〈以下、パワハラ〉の総称として使っています)。
ただ、本連載は、裁判沙汰になったあからさまなハラスメント事例を紹介してその法的論点を解説することはしません。また、「こういうことをするとハラスメントになります」といった、“べからず集”的な解説もしません。あくまでも、職場で部下指導に当たる立場の人たち(以下、このような人たちのことを管理職と呼びます)のために、ハラスメント問題についてのモヤモヤとした疑問を解消することを主眼としています。私はここ10年ほど、企業内研修の講師として働いてきました。扱うテーマはコンプライアンスと企業法務(主に契約法、労働法)とハラスメント問題です。ハラスメント研修の依頼は10年ほど前からコンスタントにありましたが、当初はそれも一時的なブームのようなもので、いずれ依頼件数は減っていくかもしれないと思っていました。しかし、予想に反して、ここ数年、ハラスメント研修の依頼は増加しています。それだけ、多くの企業がハラスメント問題に感心と危機感を持っているということでしょう。
ハラスメント研修を実施する際には、研修を企画・ 発注した事務局の方々と事前に打合せを行い、社内のハラスメント問題についていろいろな話をお聞かせいただきます。そして、そのやり取りを通じて気づいたことがあります。それは、ほとんどの企業では、相談窓口や通報制度のなかのホットライン等に上がってくるハラスメント問題の件数は非常に少なく、そのうち何らかの人事処分に至ったあからさまなハラスメントはさらに少ないという事実です。
さらに、実際の研修においては、ケーススタディや質疑応答を通じて、受講者のハラスメント問題に関するさまざまな疑問をうかがいます。そこで感じたのは、受講者が直面し頭を悩ませているのは、あからさまなハラスメントではなくグレーゾーン問題だということです。
あからさまなハラスメントについては、問題となっている行為者の言動がハラスメントになるか否かの解釈についてだれも悩むことはありません。もちろん、 行為者をどのように処分すべきか、相手方に対してはどのような救済措置を取るべきかといった悩ましい問題はありますが、それは会社として対処すべき懲戒事由の問題であって、職場の管理職が対処することではありません。
それに対してグレーゾーン問題は、日常の職場環境に内在、潜在する問題であり、管理職が、ときには行 為者としての立場で、また、ときには相手方としての立場で日々直面していることであり、問題となっている行為者の言動がハラスメントになるか否かの解釈について行為者も相手方も明確な結論が出せないために、 職場にモヤモヤとしたわだかまりや険悪な雰囲気を醸し出してしまうものなのです。
企業としてハラスメント問題に取り組むということは、職場からハラスメント問題をなくして働きやす い環境をつくるということです。そのためには、以下の方針でのぞむことが肝要です。
①ハラスメント問題をあからさまなハラスメントの分野とグレーゾーン問題の分野とに分けて認識する。
②あからさまなハラスメントとグレーゾーン問題のそれぞれについて予防法と対処法を明確にする。
③そのなかでも特に、グレーゾーン問題については綿 密に取り組み、管理職に対してその予防法と対処法 をわかりやすく示す。
あからさまなハラスメントとは ?
グレーゾーン問題とは ?
では、あからさまなハラスメント・グレーゾーン問 題とはどのようなものでしょうか。
あからさまなハラスメントとは、ひと言でいえば、 定義に当てはまることが明らかであり、10人いれば
10人とも「それはハラスメントだ」と断言できるよう な言動です。裁判沙汰になったケースなどがあからさまなハラスメントであり、その具体的な内容は容易に イメージできると思います。次回以降では具体的な事例を示しながら説明していきますが、今回は前述の要約でとどめておきます。
グレーゾーン問題とは、要約すれば、以下のような状況を指します。
●行為者にはハラスメントの意図も認識もない。
●行為者の言動も、客観的にみれば、ハラスメントだと断言しにくい。
【Episode1:君が男だったらな発言】
●司法試験を目指している M子さんは、生活費を稼ぐために派遣社員として企業法務関係の仕事をしながら受験勉強していた。●ある時期、M子さんは X社の法務部に派遣社員として勤めていて、派遣先責任者の Y部長の指示に従って Z課長の下で働いていた。
●Z課長は謹厳実直な性格で、仕事にもまじめで、 およそセクハラとは縁遠い人物であり、そのことは Y部長も M子さんも認めていた。
●一方、Z課長は常日ごろの M子さんの仕事ぶりを見て、M 子さんの能力と性格を高く評価していた。
●ある日、Z課長が M子さんと業務上の話をしていたとき、いつものように M子さんの分析力と提案内容に感心したので、M子さんを褒めるつもりで、次のように言った。
「いつもながら君のレポートはよくまとま
っているね。ホント、君が男だったらなぁ」
●そのときM子さんはZ課長には何もいわなかったが、その翌日、Z課長の上司であるY 部長に面会し、次のように言った。
「Y課長にセクハラをするつもりのないことはわかっていますし、私のことを褒めてくれていることもわかっています。でも、Y課長の発言はセクハラだと思うので、部長からY課長に注意してください」
【Episode2:定例飲み会】
●Xさんは、営業部のチームリーダーで、2人の中堅社員と 4人の若手社員を束ねている。●Xさんは、最近自分のチームで顧客からのクレームが続発している事態を重く受け止めていた。
●クレームの発生原因は何かと考えたところ、おそらく、顧客と直接やり取りをしている若手社 員と、その報告を受けて業務をまとめている中堅社員との間の報・連・相がスムーズに行われて いないからだろうと思いあたった。
●X さんは、顧客からのクレームをなくするためにはチームのコミュニケーション状況をなんとか改善しなければならないとあれこれ考え、1つのヒントを思いついた。
●それは、昔まだ自分が新入社員だったころ、仕事が終わったあとに先輩や上司に飲み会に連れて行 ってもらい、酒の席でざっくばらんに話すことにより、先輩や上司とスムーズにコミュニケーションがとれるようになったという思い出だった。そこで X さんは、中堅社員のなかのリーダー的なY さんを呼んで、次のように申し渡した。
「近ごろお客さんからのクレームが増えているのは、チーム内のコミュニケーションがうまくいっていないからだと思うんだ。
そこで、コミュニケーションを円滑にするために、今後、毎月第 3木曜日を定例飲み会にしようと思う。
定時(午後 6時)には仕事を終えて6時半までに隣の居酒屋に集合してくれ。費用は会議費で賄う。
明後日が第3木曜だから、さっそく明後日から実施するので、ほかのみんなにそういっておいてくれ」
● すると Y さんは、「それって、パワハラっぽいですね」と反応した。
ハラスメントのグレーゾーン問題とは
●問題となっている行為者の言動がハラスメン
トになるか否かの解釈について行為者も相手方も明確な結論が出せないために、職場にモヤモヤとしたわだかまりや険悪な雰囲気が残る
このようなグレーゾーン問題に対処きしれずに放置しておいたら、職場にどのような弊害が生じるかを 考えてみてください。
相手方(Episode1のM子さん・Episode2のYさん)には、モヤモヤとした気持ちが解消されないために、メンタルヘルスの不調に至ってしまう可能性があ ります。一方、行為者(Episode1の Z 課長・Episode2のXさん)には、相手や職場全体のためによかれと思った自分の言動がなぜハラスメントといわれなければならないのかという疑問が生じ、それが高じると「ハラスメントといわれるのは面倒だから部下指導はやめておこう」という考えを抱いてしまう可能性があります。そして、この2つ目の可能性は、非常に深刻な問題を含んでいます。
企業は、従業員などの構成メンバーが替わっても自 社の製品・サービスの質は維持向上させていかなければなりません。そのためには、職場における管理職による後進育成・部下指導が必須です。その任務を担っている管理職が部下指導に消極的になることは、企業にとっての「致命傷」を意味します。
本連載では、このようなグレーゾーン問題に焦点を 当て、その対処法と予防法について解説していきます
(もちろん、あからさまなハラスメントを無視するということではなく、次回以降であからさまなハラスメントの対処法と予防法についても触れますが、あくまでも必要最小限の範囲にとどめます)。
問題を考える際の前提認識
グレーゾーン問題を考える際には、その前提として次の3つの認識が必要です。これらの前提をしっかり と認識していないと、考えが誤った方向に向いたり、 無駄な思考を重ねたり、的外れな結論に至るなどの落とし穴にはまってしまいます。
1『. 目的』を明確に意識する
前述のとおり、企業としてハラスメント問題に取り組む目的は、職場からハラスメント問題をなくして働 きやすい環境をつくることです。もう少し具体的にいえば、管理職が相手にハラスメントと思わせない接し 方を身に付けて、自信を持って正しい部下指導ができ るようにすることです。また、管理職から指導される 相手方の人たちがむやみに「ハラスメントだ」と反応 する状況をなくしていくことです。企業としてハラスメント問題に取り組む際には、この目的を踏み外して はなりません。
アルハラ、スメハラ、モラハラ、テクハラなどなど、 ハラスメントを表わす4文字言葉は数々ありますが、 それらはいわば言葉遊びであって、企業としてのハラスメント問題への取組みにおいては何の意味もなく、
それぞれの意味内容を解説しても、職場からハラスメ ント問題をなくして働きやすい環境にすることにはなりません。
また、裁判になった事例や新聞で報道された事例を 紹介することも、ハラスメント問題への取組みとして は効果が弱いと思うべきでしょう。そのような事例は あからさまなハラスメントであり、そのようなことをしでかす非常識な人はごくまれであって、大多数の 人々はそういった例とは無縁なのです。
2『本質論』を把握する
企業は職場からハラスメント問題をなくすためにさまざまな取組みをするわけですが、では、職場から 除去しようとする問題とは、そもそもどのようなもの なのでしょうか。
そのようなハラスメント問題の本質論を明確に押さえておかなければ、企業として対処をする際の取組 みも、腰が定まらずにふらついたものになってしまい ます。ハラスメント問題の本質論は、以下のように認識すべきでしょう。
職場とは、従業員が企業目的に参画し貢献することにより精神的・経済的満足を得る場所です。職場を運 営していくためには、企業目的達成のために必要なこと、有益なことは実行しなければなりません。また同
時に、企業目的達成のために有害なこと、あってはな らないことは回避・改善・除去しなければなりません。 企業目的達成のために有害なこと、あってはならないことはたくさんあります。たとえば、業務プロセスに無理や無駄があってはいけません。また、いかに売上げのためとはいえ、法令違反の手段は許されません。 そのほかにもたくさんありますが、そのなかに、職場の和を乱す言動も含まれます。なぜならば、職場とは
1人の人間で完結するものではなく、必ず役割分担に 基づいてお互いの役割を認識、尊重し、意見交換、情報交換しながら企業目的達成のために協力し合う場所 だからです。この、職場の和を乱す言動を「ハラスメント」と呼んでいるのです。
つまり、ハラスメント問題の本質とは、職場を運営していくうえであってはならない言動なのです。ハラスメント問題にはセクハラとパワハラがありますが、 セクハラにせよパワハラにせよ、この本質論において は同一です。企業としてハラスメント問題に取り組む 際には、常にこの本質論を踏まえて考えなければなりません。
3『言葉の武器化現象』を理解する
「言葉の武器化現象」とは、以下のような事象を指します。
●ある言葉がつくられ、それが流行語となる
●やがて、その流行語が何らかの言動を非難攻撃する ための「言葉の武器」として使われるようになる
●それによって、それまで常識とされてきたことが非 常識となり、あるいは、それまで問題とされていなかったことが非難の対象となる
わかりやすい例としてはタバコがあります。1980年代まで、いや、1990年代の中盤あたりまで、 日本社会においてはタバコを吸うのが当たり前でした。タバコは大人のたしなみであり、タバコを吸わない成人は奇異な目でみられたものでした。
駅(地下鉄以外)の柱には灰皿が据え付けられており、皆タバコを吸いながら電車を待っていたものでし
た。食堂に入るとメニューの脇には灰皿が置いてあり、 皆タバコを吸いながら注文の品が運ばれてくるのを 待っていたものでした。職場でも喫煙者のデスクには灰皿が置かれていて、皆タバコを吸いながら仕事をしていたものでした。
ただ、駅でも食堂でも職場でも、煙草を吸っている人の周りには、その煙を不快に感じていた人もたくさ んいたのです。しかし、いくら不快に感じていても、 その不快感を口に出して主張することはできませんでした。なぜなら、タバコを吸うのが常識の世の中だったからです。また、タバコに対する不快感を言い表す言葉もなかったのです。
ところが、1990年代終盤から 2000年代初頭にかけて、「受動喫煙」という言葉がつくられ、それによりそ れまで自分の気持ちを表わすことのできなかった非喫 煙者が「他人のタバコの煙で自分の健康が害されるのはたまったものではない」という非難の声をあげることができるようになりました。
その結果、「タバコは吸って当たり前」という常識が 否定され、いまは「タバコは悪」という常識の世の中になったのです。
ハラスメント問題にも、この「言葉の武器化現象」がみられます。次回以降でも詳しく触れますが、いま私たちがセクハラやパワハラのあからさまなケースとし てイメージするような出来事は、いわば「イジメ」という事象であり、ヒトが猿から進化して集団活動を営む ようになった大昔から存在していたのです。
たとえば、時代劇に登場してくる越後屋の旦那。女 中を手込めにしようとして拒絶され、腹立ち紛れに
「おまえなんぞに用はない、国へ帰れ !」と解雇してしまうような商家の主は実際に存在したのでしょうが、 その振舞いはまさにセクハラそのものです。
また、織田信長は、織田家の重臣の宴席で明智光秀 が「ようやくわれわれも天下平定まであと一歩のとこ ろまできましたな」と言ったそのひと言に激しく腹を立て、「この金柑頭め(註:禿げのこと)、ここまできた のはうぬのせいではないわ! うぬぼれるのもたい
グレーゾーン問題を考える際には、
3つの前提認識が必要
●「本質論」を把握する
●「言葉の武器化現象」を理解する
がいにせい !」と言いながら明智光秀の頭を小突き回したというエピソードがあります。これが本当なら、 明智光秀に対する織田信長の言動はまさにパワハラそのものです。
わずか10年前、20年前の日本企業における職場の状況を思い出してみても、いま私たちがセクハラやパワハラと呼んでいる状況はたくさん存在していました。 そして、その状況のなかで不快感を感じた人々やつらい思いをした人々もたくさんいたのです。しかし、その当時はいま私たちがセクハラやパワハラと呼んでいる状況が常識だったり、あるいは、職場から除去すべき問題として認識されていなかったために、ある言動に不快な思いをしてもそれを口に出して言えず、つらい思いをしても泣き寝入りするしかなかったのです。ところが、ある時期にセクハラという言葉が誕生し、 また別の時期にパワハラという言葉が誕生し、それが流行語として使われたことにより、ある言動に不快な思いをしていた人々や泣寝入りしていた人々がもう黙っていることなく、その言動を非難するようになったのです。
ハラスメント問題の根底には、この「言葉の武器化現象」があります。ハラスメント問題に向き合うとき、「言葉の武器化現象」という視点で考えるという認識も 持っておいてください。
以上、述べてきたことを踏まえ、次回以降、セクハラ問題・パワハラ問題それぞれのあからさまなケース とグレーゾーンのケースについて深掘りし、その予防法と対処法について解説していきます。また、職場からハラスメント問題を除去するためには、職場の管理 職がハラスメント問題の予防法と対処法を身に付ける だけでは足りず、いわゆる「組織的対応」も必要不可欠 ですので、本連載の最後では「組織的対応」について詳しく述べたいと思います。

アーサーアンダーセン、アンダーセンコンサルティング、リシュモンジャパン株式会社等の外資系企業の総務・法務部で契約書作成・レビューを中心とする企業法務業務に従事。その後、KPMGあずさビジネススクール株式会社で研修講師を務め、現在は株式会社インプレッション・ラーニングにおいてコンプライアンス、企業法務を中心とする講師を務める。主な著書として、 『現場で役立つ !ハンコ・契約書・印紙のトリセツ』『現場で役立つ !セクハラ・パワハラと言わせない部下指導』(日本経済新聞出版社)等。

